
ちわ、おいさんだよ。
キミは宮本武蔵を知っているかい?
まぁ、それなりに知ってるけど、それが何か?


ふりかえってみると、わしの人生に影響を与えた本を挙げると若い頃に読んだ本で「五輪書 (講談社学術文庫)」と「徳川家康(山岡荘八歴史文庫)
」の二つなんだけど、今回はその「五輪書」について語ってみたいと思うのじゃ。
青春時代に影響を受けた一冊ってことかw

前回まではこちら
背景画像を書きたい人のための本だよ。という話(*´ω`*)
-

-
背景描くのに最適な背景グラフィッカーのための入門書
続きを見る
五輪書
|
わしが中学生の頃、バガボンドブームが起こった。
「バガボンド」とは、いわずもがなスラムダンクの作者である井上雄彦氏が吉川英治の「宮本武蔵」をベースにして描いたマンガのことである。
その時、周囲の人間はマンガにばかりハマッていたけど、わしは一歩進んで本当の宮本武蔵像なるものは一体どういうものだったのか触れてみたくて色んな宮本武蔵関連の本を読み漁っていたのだった。
朝の読書に五輪書
その内の1冊に「五輪書」はあった。
今考えて見ると、中学生で五輪書を朝の読書の時間に読んでいたなんて、随分生意気なガキだったように思えるが、当時は必死に、それこそ貪るように武蔵の言葉を吸収していたものだった。
ただわしが買った五輪書は、ハードカバーで薄い和紙で周りを装丁されたなかなか豪華なもので、内容も原文と邦訳分が交互に収録されていて、中学生が読み解くにはかなりハードルが高いものだったw
しかし、バカにはバカになりに、わからないならわからないなりになんとか必死で辞書を引きつつ熟読していたのを昨日の事のように覚えている。
ただその内容になると、もう半分以上も忘れてしまっているけど、それでも当時はそうした剣豪の生の声を聞いたような気がして胸がわくわくしたものだったw
多角的な目線を忘れない
そんな武蔵の言葉の中で一番覚えているのは、確か「道を極めるためにはあるところで別の道を進んでみなければならない」というようなことが書かれていたことだ。
これは剣を極める者なら剣のみに執着するのではなく、あるレベルまで到達したらそこから別の道に進み、様々な観点から客観的に自分が進むべき方向を見ていかなければならない。というような意味合いだったと記憶している。
事実武蔵も途中で書や絵画に傾倒し、その道では当時なかなかの腕前になりながら、そうした経験は剣の道にも大きな影響を与えたと言っている。
真に道を極めようとするものは、それ一つに執着するのではなく、たまには別の何かをすることによって己の未熟さを確認することがきっと大切なのだろう。
そんなことを、まだ若い中学生のわしは悟ったのだ。
あれから十数年、わしもいい加減もうすぐ30に手が届きそうな歳だが、悟ったはずのわしが今や色んな道に進みすぎて自分に迷ってばっかである。
どうやら五輪書は、未熟なわしには早すぎた書であったらしいw
……もう一度、読み返してみるか(;´∀`)

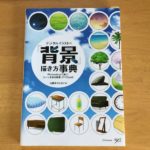
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/14c31374.67a3252e.14c31375.40e6ca48/?me_id=1213310&item_id=10151175&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7359%2F9784061587359.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7359%2F9784061587359.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)




